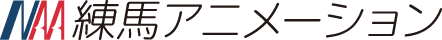第14回:宇田鋼之介氏(アニメ監督、演出家)のアニメ「履歴書」《その2》
自主制作でドタバタしていた姿をどの様に見ていたのか、当時、専門学校の講師をされていた方から「ウチに来い」と誘いを受け、就活などまだ何も考えてなかったので曖昧に返事をしていたら、いつのまにかそのスタジオに入社することになっていました。在学中から出社し、「ほのぼのレイク」のCMの制作進行からプロとしてのキャリアをスタートさせることになったのですが、何しろ突然のプロの現場ですから知らないことだらけでドジの連続。もう、ね、混乱と反省しかなかったです。しかしながら不思議と辛いという気持ちは全く起きませんでした。
プロになったという高揚感もあったのでしょう。毎日が新しく知る事だらけだったのでむしろ楽しいとすら感じていました。マア、「水が合った」とでも言いましょうか。この業界が自分にとって「居心地が良かった」というのが一番の理由だったと思います。
今この歳になっても、この「居心地が良い」というのは、とても重要だなと思います。
あれからン十年の年月が流れてアニメ業界も大きく変化しましたが、ある種の体臭のような「業界の空気」はあまり変わっていません。このことの是非はまた別問題ですが、この「業界の空気」に馴染めるかどうかもある意味必要な資質だと感じます。事実、優秀な能力を持ちながら(言葉は違っても)このことを理由に去っていった人を多く見てきました。ちょっとシビアな話でしょうか? この話はまた別の機会にお伝えできればと思います。
春先になって、所属スタジオの社長より「東映動画(現、東映アニメーション)から出向で人が欲しいと連絡があったが、お前、行くか?」と言われました。アニメ作りの本流を学びたいと思っていたのでコレは願っても無いチャンス。即座に「行きます」と返答しました。
じつは専門学校時代、マシンがけ(動画の線を機械とカーボン紙を使ってセルロイドに写す作業)のバイトで何度か東映動画にはお邪魔していました。しかし、スタッフルームに入って作業するのは初めてのことなので、改めてくぐる正門はドキドキでした。このこともまた大きな転機になりました。
案内された現場は「劇場版 トランスフォーマー」(トランスフォーマー ザ・ムービー)。マーベルと東映の日米合作の映画です。
制作状況は終盤に差し掛かり始めた頃で、原画チェックから撮出しまで、いろんな作業が並行して行われている状況でした。任された仕事は「演出助手」。とはいっても助手の助手の助手みたいなポジションで、監督や助監督から指示された作業をこなす仕事です。「Zマスク」作り、「リスマスク」作り、「背景から型をとっての透過光マスク」作りなど、業界人でも40歳未満だったら「何ですかソレ?」と言われるような作業が主な仕事でした。アナログ時代の話ですからね。今はもう無い作業です。
さていよいよ作品作りも大詰めになって来ると、作業量が尋常ではなくなってきます。気が付いたら深夜になってることはもう当たり前で、蓄積された疲労によってみんな段々殺気立ってきます。けれど劇場版のカット数とセルの量はハンパなく多く、終わりがちっとも見えません。この作品が終わることは無いんじゃないか、と本当に思いました。いや、必ず終わる日は来るんですけどね。制作進行で歳が一緒だった五十嵐卓哉君(現、ボンズ)とよく「ネバー・エンディング・ストーリー」を歌ってました。
大変な作品でしたけど、この時の経験は後々自分に踏ん張る力を与えてくれました。
作品が完成した時、監督だった森下孝三さん(現、東映アニメーション会長)に呼ばれて、パイロット作品の制作進行兼演出助手として東映に残ることになりました。いや、単に人手不足だっただけなんですけど、ポジティブに捉えてます(笑)。
そしてその作品が終わる頃、TVシリーズのトランスフォーマー班に組み込まれ、こうして、出向ではありましたが「なし崩し的に」東映動画で働くことになったのです。
東映で働くことが出来たのはとても幸運な出来事だったなと今でも思います。何しろスタッフの数が多く、撮影・編集といったセクションまで同じ建物にありましたし、同期から大先輩まで様々な方々とお話をすることが出来たのは、自分にとって掛け替えのない財産となりました。技術や知識だけでなく、作品に対するある種の哲学、矜持といったものまで、ありとあらゆる刺激を受けることが出来たんですから。
もともとアニメに関する知識が乏しかった分、知る面白さは人より大きかったのかもしれませんね。東映だからといってギャラが高かったわけではありません。正直、貧乏生活でした。苦ではなかったと言えば嘘になりますが、それを凌駕する楽しさが現場にはあったなと思います。資料室に行くと子供の頃に熱中した作品のコンテやらキャラ表やら原画やらもあり、それらに見惚れ、何時間でも籠っていられる気分でした。
しかし、そうして何年かすぎると日々は当たり前になり、忙しい毎日にすっかり情熱は削ぎ落とされて、将来についても考えるようになってきました。収入のことも輪をかけます。演出助手として作品に何本も関わり、その度に新鮮な思いはするのだけれど長続きはせず、「この、いま受け持ってる話数を最後に辞めよう・・・」と思いながら単純にキッカケを失ってるだけになっていました。
次回は、佐藤順一さんとの出会い、演出デビューとその後についてお話しします。
宇田鋼之介(アニメ監督、演出家)