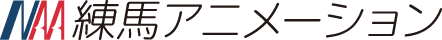第17回:堀川和政氏(東映アニメーション)のアニメ「履歴書」《その2》
演助進行という仕事は、原画の演出チェックが終わった後に、演出助手としての原画チェック=キャラクターのコスチュームや小物などの統一や撮影シート上のカメラワークの指定などをしつつ、個々の演出の癖を盗み演出方法についての勉強もする一方、進行としてキャラクター設定の発注から作画監督との交渉、原画の発注から回収及び動画の発注から回収、仕上げ、背景への発注から上がりまでのスケジュールの管理、更に仕上上がりと背景上がりを合わせての撮影出し、撮影上がりのチェック、編集時間の調整・設定、撮影リテークの処理、撮影済みカットの回収…と作品製作の最初から完成まで、係わる仕事とその量において、1話を作る中で一番濃い仕事であることは間違いない。私はこの後、演出の道へ進むわけだが、演助進行という仕事は演出として1本作品を作ることより、アニメの製作とはこういうものなんだということを誰よりも理解する上で、また社内外の人々にそれを伝える上で、最強の職種と思っている。同時に、作品を作る上で凝るところは凝る、丁寧に作るところは手を抜かない、一方、限られた時間の中で削れる部分は削る、あるいはそれなりのところに収める、というクオリティと制限時間とのバランスを考慮して仕事をするという知恵も、この時期に身につけた。がしかし、このバランスをとる上で、あくまで自分が演出として、自分の作品に強いこだわりをもって、それを極力譲ることなく、作画や背景、撮影などで貫き通せるかどうか、これが演出としての「生命線」でもあるということも理解できた。別の言い方をすれば、それぞれの工程に携わる多くの人々に負担を強いることなどは考えずに、自分のやりたいようにやるくらいでないと、演出家としていい作品を作ることは出来ないというのも事実であり、その後、演出を経験するも製作管理の道へ転じた大きな理由ともなった。よって、演出という職業において、演出法というものを深く追求するには至らなかった。だが、演出する上での苦労とか、演出上の技術とかポイントについて一定の見識が身についたことは間違いない。撮影技法などは得意中の得意であったが、シナリオの内容、展開、心理的な側面を反映したカットの構成などに対しては、未熟な映像を残してしまったことが悔しいところである。反面、某作品でメインキャラがやられる瞬間をストロボTUで効果的に見せ、絶賛された記憶は今でも鮮明に蘇る。
製作管理に転じた後は、演出まで経験した知識を生かし、アニメ製作について全方位に渡って目を行き届かせることに注力した。よい作品作りをする上での、押さえるべきところは押さえ、一定のクオリティは確保するという、常にスケジュール的余裕がないアニメ製作の現実の中での製作の進め方、管理を実践できる、社内でも稀少な存在であったと自負するところである。とは言え、どの仕事もそうであるように、中心にあるのは人の管理であるので、常識のない、あるいは常識のずれている人間が多いこの世界で、その人達と付き合い、作品を作っていくというのは苦労の絶えないところであった。そのためか髪の毛も減っていき普通の人より早く枯れてしまったのである。
髪の毛がまだふさふさであった頃の苦労とは別の、今もよき思い出となって残っていることがある。それは「デジタル製作プロジェクト」である。紙で製作するアニメ製作を、コンピューターの発展目覚しく、PCも職場に普及が進んでいた時期、既にPCによる作画から撮影までの作業をソフトウェア化したセルシスと、NTT、日立といった大企業を交えた4社連合で、ネット専用回線を都内のアニメスタジオと結び、製作工程までPC上で管理してしまおうというプロジェクト。各社からは精鋭が顔を揃え、私はそのプロジェクトの担当者となり、システム作りに日夜取り組んだのである。
当時、動画の自動中割りも他社で開発が行われ、テレビ報道されたりもして、デジタル化への機運は大いに高まっていた時期であり、4社連合のプロジェクトも喧々諤々ありながらも一定のところまで開発が進んでいった。しかし、2つの点で躓いた。1つは、PCで製作工程を管理する本システムにおいて、撮影までいったカットが作画直しなどのリテークになった場合に、工程を遡ることに対応できないという思いもよらない事由。もう1つは、練馬区内を中心とした製作スタジオとのネットワーク化で、作画スタジオに対しては、専用線を繋ぎデジタル作画用のペンタブレットを無料で配付したのだが、貸し出すだけで、デジタル作画の習得から実践に移行する間の賃金の手当てに手を差し伸べなかったこと。アニメーターは歩合制で、1カット3000~4000円で原画を描いたカット数分だけが月々の収入となるため、デジタル作画を習得するのに時間を使い、当の原画をやる数が減ってしまえば収入が激減し生活できなくなってしまうのである。これに対しては、当然何らかの補償をしてやらないことにはデジタル作画を習得しようなんてことにはならないのであるが、会社はその出費をためらい、補償手当てを出さなかった。こうして、折角業界で先んじて取り組んだ意義ある試みではあったが、頓挫してしまったのである。しかし、工程管理システムは実現できなかったものの、デジタル仕上げについては、当社が先んじて始め、その効率の良さはセル仕上げとは雲泥の差があり、実績を積んだことから、様子見であった業界各社は雪崩をうってデジタル仕上げに参入、移行していったのである。そうしてデジタル仕上げからデジタル撮影までをアナログから切り替えるのに環境が整ったタイミング=当時の「ゲゲゲの鬼太郎」で、1話全体での切り替えを実行に移した。当時、デジタル作業において、特に撮影での合成処理には、撮影終了の予測が立たなくなるという懸念があった。複雑な撮影内容だと、マシンの計算処理が著しく遅くなるためである。そのため、「仕上のアップを撮影アップの1週間前に必ず終わらせる」というスケジュールを確実に守らせるために、その履行を関係先との間に入って押さえ、実行し、オールカラーでのアフレコを実現させたのであった。当時、デジタル化にあたり、そこまで徹底したスケジュール管理も、その後、デジタルゆえの便利さ(=仕上げ直しも撮影直しも、すぐその場で出来てしまう)をいいことに、引っ張ってはいけない仕上げアップの押さえ、撮影アップの押さえをぎりぎりまで使うことになってしまい、現在の納品ぎりぎりから逆算して作業を引っ張るやり方が横行しているのは情けない限りである。
そういえば、私が演出から製作に転じてまもなく、初代編成課長になった時、製作担当の仕事から離れ、製作作品全体の編成業務に専念しなさいという会社指示の元、半年余り当該業務に当たっていた矢先、突然、秋から始まるテレビシリーズの製作担当がいないから兼務して当たるようにということになった。この作品は製作決定のスタートが遅れに遅れた結果、1話のシナリオ決定稿が8月のお盆の最中となり、演出にはコンテに直ぐにかかってもらい、順次、作画打合せやらキャラ設計上げやらを無理に無理を言ってやってもらい、10月初旬の1話の放送に間に合わせたことがあった。
たった7週間で1話を完成させたのである。この時ばかりは、どうだと言わんばかりの「やってやったぜ!」な気分になったものだった。また、スタッフにゴールデンウィークや盆休みをしっかり取ってもらうために「アフレコ2本録り」を行い、1話分の納品ストックを確保する必要があるのだが、この時は全話数のスケジュールを1週間繰り上げて製作していかなければならなかった。アニメーターや現場スタッフには自分で放送日から逆算したギリギリのスケジュールで動いてしまう癖があるので、それをさせないために、強い意志で関係スタッフの引き締めを行い、まとまった休暇の確保をしたものだ。しかし、あの時はみんなよく頑張ってくれた。無理言ってごめんね、有難うと今も思う。そういうアニメ製作の数々の歴史の積み重ねがあり、今日の会社の繁栄があることを、今の繁栄しか知らない者たちは、しっかりと認識しなければならないのだよ。
しかし、アニメ製作の現場にいた頃はまだ幸せであったのだ。
次回は、総務への異動と最後の大仕事、そして定年を前に思うことについて、お話しします。
堀川和政(東映アニメーション)